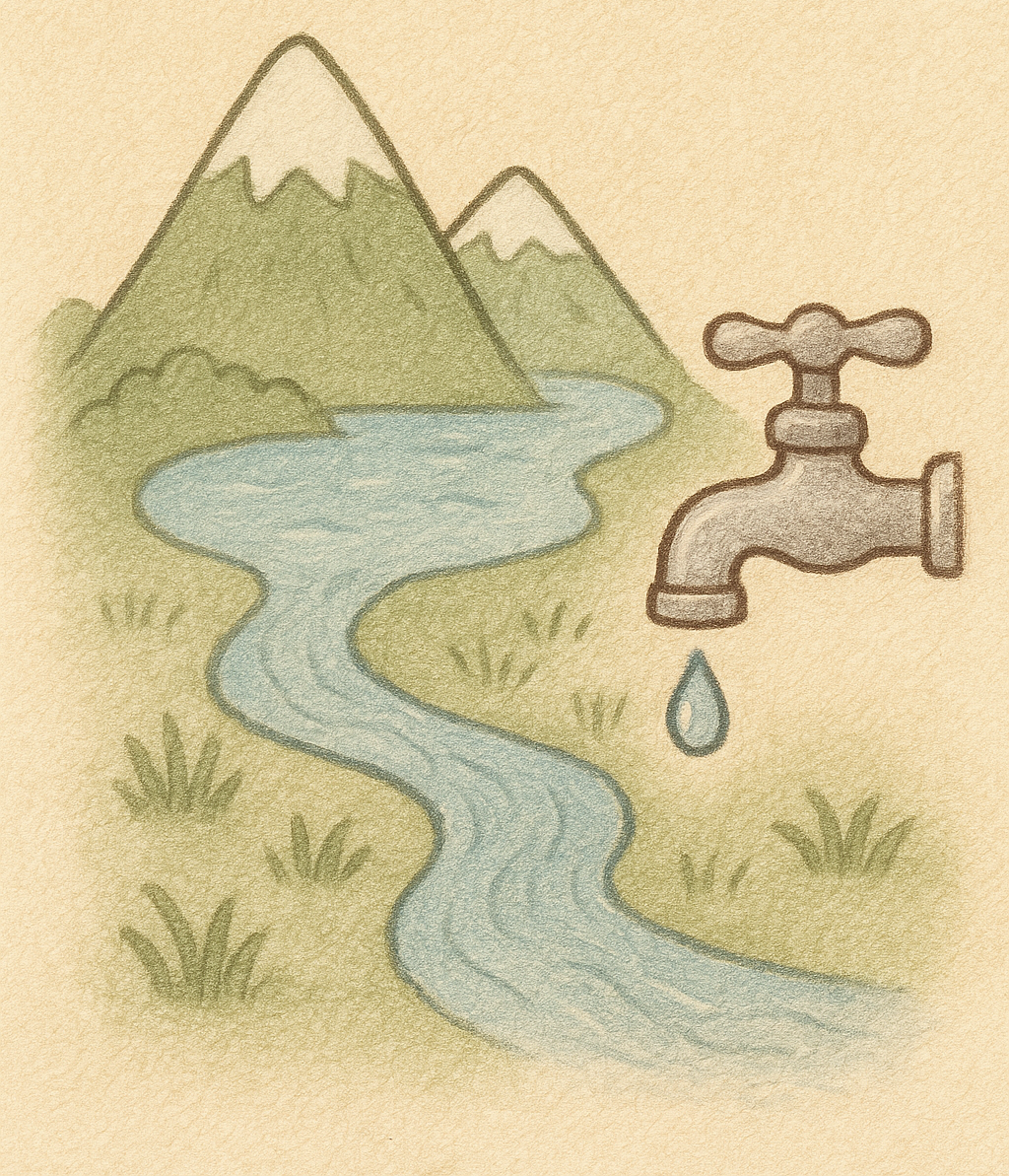第30回問01~問05の解き方
第30回キャリアコンサルタント試験学科試験問題を徹底解説!
選択肢の正誤と解説、参考文献をお伝えします。試験対策にお役立てください。なお、過去の類題の過去問解説のリンク先の内容は、直近3回分以外はみん合☆プラス会員限定公開です。
解説内のページ数の表記(【P××】)は、出典の官公庁資料、出典と思われる専門書などの参照ページ数を表しています。また、A(易しい)、B(差がつく)、C(難しい)の難易度評価を記載しています。
目次
問1.社会及び経済の動向並びにキャリア形成支援の必要性の理解
【C】定番の労働経済の分析からの出題ですが、やや細かな内容が出題されており、自信を持って判断できる選択肢は少ない問題でした。50問中の1問でしかありませんから、問1では出鼻をくじかれないようにしましょう。
正答:4
1.×:高齢者を中心に2022年時点で約3,000万人の就業希望のない無業者が存在するが、年齢に限らず総じて女性が多い。【P148】
2.×:59歳以下の女性の非就業希望の理由としては、「出産・育児・介護・看護・家事のため」の割合が最も高い(約4割)。【P148】
3.×:非求職理由として最も割合が高いのは、59歳以下の男性は「病気・けが・高齢のため」であり、59歳以下の女性は「出産・育児・介護・看護のため」である。【P149】
4.○:求職期間が1年以上の男性は約3割、女性は約2割に達している一方で、求職
期間が1か月未満の短期の求職者も男性で約3割、女性で約4割を占めており、求職の状況が二極化している可能性がある。【P149】
問2.キャリアコンサルティングの役割の理解
【A】前回に続き、「キャリアコンサルティングの役割の理解」の出題範囲からは、能力開発基本調査の出題でした。予想通り、令和6年度版からの出題でしたが、問12では令和5年度版からの出題もありました。
正答:2
1.×:そこまで高くない。労働者全体で、毎年概ね1割程度である。
令和5年度中にキャリアコンサルティングを受けた者は、労働者全体では11.7%であり、正社員では13.9%、正社員以外では6.3%であった。【P67】なお、選択肢では「令和4年度中」とあるが、令和4年度中の記載は本資料の中にはない。
2.○:キャリアに関する相談をする主な組織・機関は、「職場の上司・管理者」の割合が最も高い(正社員72.5%、正社員以外67.1%)。【P67】
3.×:正社員、正社員以外ともに、「仕事に対する意識が高まった」が最も多い。【P67】
4.×:正社員と正社員以外が逆である。
正社員では「将来のキャリアプラン」が最も多く、「仕事に対する適性・適職(職業の向き不向き)」が最も多い。【P70】
楽習ノートプラスのページに、まとめ編や問題編を合計6編用意しています。
問3.キャリアコンサルティングの役割の理解
【A】こちらの資料も定番ですが、第25回問47以来の出題でした。内容を一読しておきましょう。
![]()
正答:3
1.○:労使双方が抱くキャリア観の変化や、心理面・行動面でのゆれ・ゆらぎを捉え、「働くことについての相談相手」として機能し、キャリア自律、キャリア実現の推進役を務めることが期待される。【P1】
2.○:キャリアコンサルタントには、質の高いキャリアコンサルティングを通じて、キャリアプランの再設計、新たな学び・学び直しの動機付け等に繋がるような、適切な助言・指導を行う専門性の発揮が期待される。【P1】
3.×:「よりも」表現には注意する。むしろ、連続的・長期的なキャリア形成の視点が必要である。
企業におけるキャリア開発は、企業と労働者の協働の取組として進められるべきものであるが、連続的・長期的なキャリア形成を念頭に見た場合、専門職としての知見・実践力を生かしたキャリア形成支援が期待される。【P1】
4.○:キャリアコンサルタントは、労使双方から寄せられる期待と要請に応え、更なる専門性の深化や活動領域での活躍に繋げるべく、自律的・自走的な学びと実践を積む必要がある。【P1】
問4.キャリアに関する理論
【A】社会認知的キャリア理論(SCCT)については、国家試験では久しぶりの出題ですが、直近の2級第34回問5で出題されています。相互に出題される内容も多く、2級技能検定の直近3回分は国家試験対策に役立ちます(逆もしかりです)。
正答:3
バンデューラが提唱した社会的学習理論を、レント、ブラウン、ハケットはキャリア選択に応用しました。
1.○:社会認知的キャリア理論(SCCT) では、学習経験が、人の認知に大きく影響すると考える。なお、学習経験とは、4つの情報源をもとに自己効力感を獲得する経験のことである。【ジルP34】
 職業相談場面におけるキャリア理論及びカウンセリング理論の活用・普及に関する文献調査
職業相談場面におけるキャリア理論及びカウンセリング理論の活用・普及に関する文献調査
当サイトでは通称、ジルや、ジル資料と呼んでいますが、独立行政法人労働政策研究・研修機構(JILPT:ジルピーティー)で発行している資料で、キャリア理論とカウンセリング理論がわかりやすくまとめられており、おすすめです。なお、PDFファイルは無料でダウンロードでき、移動時間等の学習に役立ちます。
2.○:社会的学習理論や、社会認知的キャリア理論においては、4つの情報源からの学習経験により、自己効力感を獲得することを重視している。【ジルP34】
自己効力感を高める4つの情報源には、遂行行動の達成、言語的説得、代理的経験、情動的喚起がある。【ジルP32】
覚え方:すいげん だいじょ
3.×:自我同一性(アイデンティティ)は、8つの発達段階と発達課題を整理した、エリクソンの「青年期」における発達課題である。
社会認知的キャリア理論(SCCT)とは直接的な関係はない。
4.○:結果予期(結果期待)は、「それを実行したらどうなるのか」という結果に対する主観的な予測のことである。
具体的には、給与や賞金、賞品などの①物理的成果、他者からの承認や称賛などの②社会的成果、自らの満足感である③自己評価成果に分類され、③の自己評価成果は努力を継続する粘り強さに関係するとされる。【ジルP34】
なお、結果予期(結果期待)は、前回の第29回問6のバンデューラに関する問題でも出題されている。
問5.キャリアに関する理論
【A】クランボルツの「偶然の出来事を捉える5つのスキル(資質)」からの出題です。
正答:2
偶然の出来事を捉える5つのスキル(資質)の覚え方。
覚え方:コージ君 柔軟に 楽しく 冒険
(好奇心、持続性、柔軟性、楽観性、冒険心)

1.×:レジリエンスは「回復力」を意味する。レジリエンス、希望、効力感は5つの資質に該当しない。
2.○:ジル資料にある「持続性(Persistence)」は粘り強さ、「冒険心」はリスクテイキング(Risk-taking)と表現されているが、適切な表現である。【ジルP47】
3.×:レジリエンスと効力感は、5つの資質に該当しない。
4.×:希望、効力感は、5つの資質に該当しない。