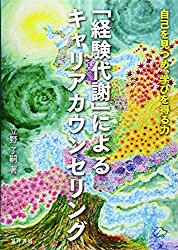教材ガイド
 参考書や問題集は購入したほうが良いのか?
参考書や問題集は購入したほうが良いのか?
これまでの「キャリアコンサルタント試験(学科)」の内容を振り返ると、学科試験対策は養成講座テキストだけでは心もとないというのが率直な感想です。
合格された方の中には「養成講座テキスト+過去問解説+みん合のまとめや問題のページ」中心の学習で見事に合格!という方もいらっしゃるのですが、多くの合格者が試験後の感想として、テキスト以外の参考書や問題集での学習の必要性を伝えてくださいます。また、実務経験の受験資格により受験される場合には、学科試験対策は完全に独学の態勢で臨むことなります。
教材選択の参考になるよう、このページでは参考書、問題集の特徴などをお伝えします。
目次
キャリアコンサルタント試験における書籍(参考書)からの出題
まず、学科試験はどんな書籍、参考書から出題されているのか?例えば、第24回試験の出典等を見てみましょう(みん合調べ)。
第24回試験で、実際に出題のあった書籍は次のとおりです。数字は選択肢数です。
| 種類 | 出題のあった書籍名 | 選択肢数 |
| 書籍 | キャリアコンサルティング理論と実際木村周著(雇用問題調査会) | 16 |
| 書籍 | 働くひとの心理学岡田昌毅著(ナカニシヤ出版) | 6 |
| 書籍 | 新版 キャリアの心理学―キャリア支援への発達的アプローチ渡辺 三枝子著(ナカニシヤ出版) | 15 |
| 書籍 | 職業相談場面におけるキャリア理論及びカウンセリング理論の活用・普及に関する文献調査(独立行政法人労働政策研究・研修機構) | 2 |
| 書籍 | マイクロカウンセリング技法福原眞知子著(風間書房) | 4 |
書籍で最頻出なのは、木村先生/下村先生共著の「キャリアコンサルティング理論と実際」。超定番参考書で、国家試験と技能検定のバイブルと言えます。毎回この書籍から多くの問題が出題されており、出典No.1です。毎回おおむね6、7問程度が、この書籍から出題されています。
上位4点は、試験出題の常連の書籍、資料と言えるでしょう。
それでは書籍、教材ごとにその特徴を紹介します。
学科試験対策の参考書編
キャリアコンサルティング理論と実際6訂版(木村周、下村英雄共著)
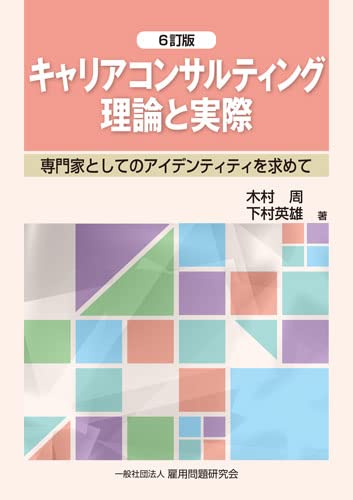 【参考書】教科書に該当する位置づけです。内容はキャリアコンサルタントに必要な知識が網羅されており、読み込むというよりは、過去問で出題された箇所を確認、参照しながら知識を整えていくと良いでしょう。2022年5月に6訂版が刊行されました。
【参考書】教科書に該当する位置づけです。内容はキャリアコンサルタントに必要な知識が網羅されており、読み込むというよりは、過去問で出題された箇所を確認、参照しながら知識を整えていくと良いでしょう。2022年5月に6訂版が刊行されました。
おすすめ指数は、![]()
日本のキャリアコンサルタントの知の礎を築いたといっても過言ではない著作で、試験対策上も外すことができない、必携の一冊です。
新版キャリアの心理学【第2版】(渡辺三枝子著)
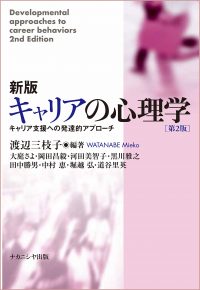 【参考書】理論家、理論ごとに章立てがされており、理論の背景なども含め、詳しい解説により理解を深めることができる、キャリア理論に特化した、試験では頻出の参考書です。
【参考書】理論家、理論ごとに章立てがされており、理論の背景なども含め、詳しい解説により理解を深めることができる、キャリア理論に特化した、試験では頻出の参考書です。
おすすめ指数は、![]()
好きな理論家、気になる理論から読み始めたり、弱点を克服するのに使いやすい参考書です。私も時折読み返していますが、資格取得後もキャリアコンサルタント必携の書といえるでしょう。
職業相談場面におけるキャリア理論及び カウンセリング理論の活用・普及に関する文献調査(労働政策研究・研修機構)
 キャリア理論とカウンセリング理論の基礎知識が網羅されており、比較的読みやすくまとめられている良質なPDF資料です。発行している団体名の略称から、私は「JIL(ジル)」資料と呼んでいます。ちなみに、PDFダウンロードは無料です。
キャリア理論とカウンセリング理論の基礎知識が網羅されており、比較的読みやすくまとめられている良質なPDF資料です。発行している団体名の略称から、私は「JIL(ジル)」資料と呼んでいます。ちなみに、PDFダウンロードは無料です。
おすすめ指数は、![]()
また、書籍(紙)版は機構での直販またはAmazonで購入できます。内容はPDF版とほぼ同様ですが、相違点のご確認はこちらのページへ。
働くひとの心理学(岡田昌毅著)
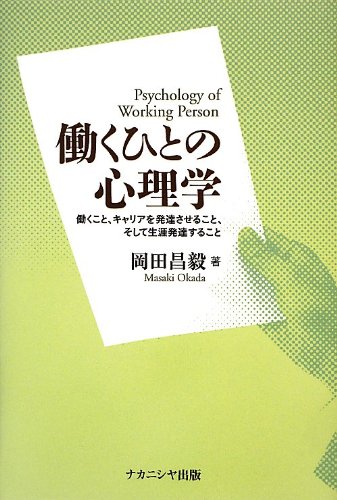 【参考書】木村、宮城、渡辺先生の書籍には無い記述がある点で参考になる書籍です。働くひとのモチベーションや成長に焦点を当てているため、特に動機づけ理論や生涯発達の理論が詳しい良書です。
【参考書】木村、宮城、渡辺先生の書籍には無い記述がある点で参考になる書籍です。働くひとのモチベーションや成長に焦点を当てているため、特に動機づけ理論や生涯発達の理論が詳しい良書です。
おすすめ指数は![]()
養成講座テキストで、上記の内容がある程度網羅されていれば、必携とまでは言えませんが、第Ⅰ部の各理論家のまとめは知識の整理に役立ちます。万全を期したい方にはおすすめの一冊です。
キャリアカウンセリング(宮城まり子)
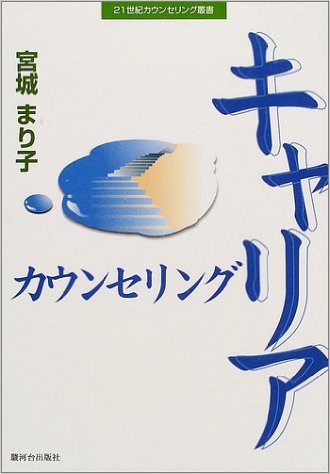 【参考書】本書は、カウンセリング理論の入門書にあたります。養成講座テキストのまとめとして、理論の繋がりや位置づけなどを再確認するための頭の整理に役立つ書籍です。また、非常に読みやすいのが特徴で、基礎固めや最初に読む一冊です。
【参考書】本書は、カウンセリング理論の入門書にあたります。養成講座テキストのまとめとして、理論の繋がりや位置づけなどを再確認するための頭の整理に役立つ書籍です。また、非常に読みやすいのが特徴で、基礎固めや最初に読む一冊です。
おすすめ指数は、![]()
一読してみると養成講座テキストの理解が深まるでしょう。また、実務経験で受験する独学の方には最初の入門書としてもオススメです。
カウンセリングの理論(國分康孝著)
 【参考書】カウンセリング理論、特に精神分析理論、自己理論(来談者中心療法)、特性因子理論、ゲシュタルト療法や論理療法などが詳しい。1980年刊行と古い書籍ですが、わかりやすい例え話などに、ついつい引き込まれてしまう名著です。
【参考書】カウンセリング理論、特に精神分析理論、自己理論(来談者中心療法)、特性因子理論、ゲシュタルト療法や論理療法などが詳しい。1980年刊行と古い書籍ですが、わかりやすい例え話などに、ついつい引き込まれてしまう名著です。
おすすめ指数は![]()
試験対策としては必要ありませんが、カウンセリング理論の基本書としてオススメです。試験後にじっくり読みたい名著です。
カウンセリングの技法(國分康孝著)
 【参考書】カウンセリングの大家、國分先生の1979年刊行の読み応えある名著。本書からの出題は、最近では第20回、21回でありました。その独特で堅苦しくなく、わかりやすい表現や明快な技法はカウンセラー必読の書と言えます。こちらも、試験後にじっくり読みたい名著です。
【参考書】カウンセリングの大家、國分先生の1979年刊行の読み応えある名著。本書からの出題は、最近では第20回、21回でありました。その独特で堅苦しくなく、わかりやすい表現や明快な技法はカウンセラー必読の書と言えます。こちらも、試験後にじっくり読みたい名著です。
おすすめ指数は![]()
読後満足感あるカウンセリングの基本書です。
キャリアコンサルティング関連情報集(キャリアコンサルティング協議会)
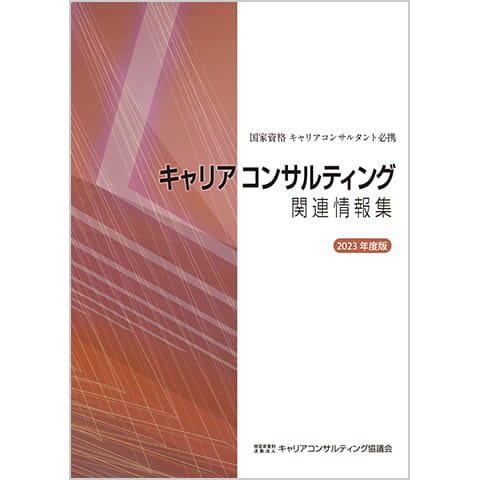
【参考書・資料集】「資料一覧」の位置づけで、官公庁資料・統計を中心に、その概要や情報元へリンクするQRコードが掲載されています。リンク先を辿りすべてを網羅することはなかなか困難でから、必要に応じて参照するのが良いでしょう。または、時事問題ダイジェストとして活用しましょう。
おすすめ指数は、![]()
購入はキャリアコンサルティング協議会へ。
KindleUnlimited会員の方は読み放題にて利用できます。こちらで電子書籍版を入手できます。
知って役立つ労働法~働くときに必要な基礎知識(厚生労働省)
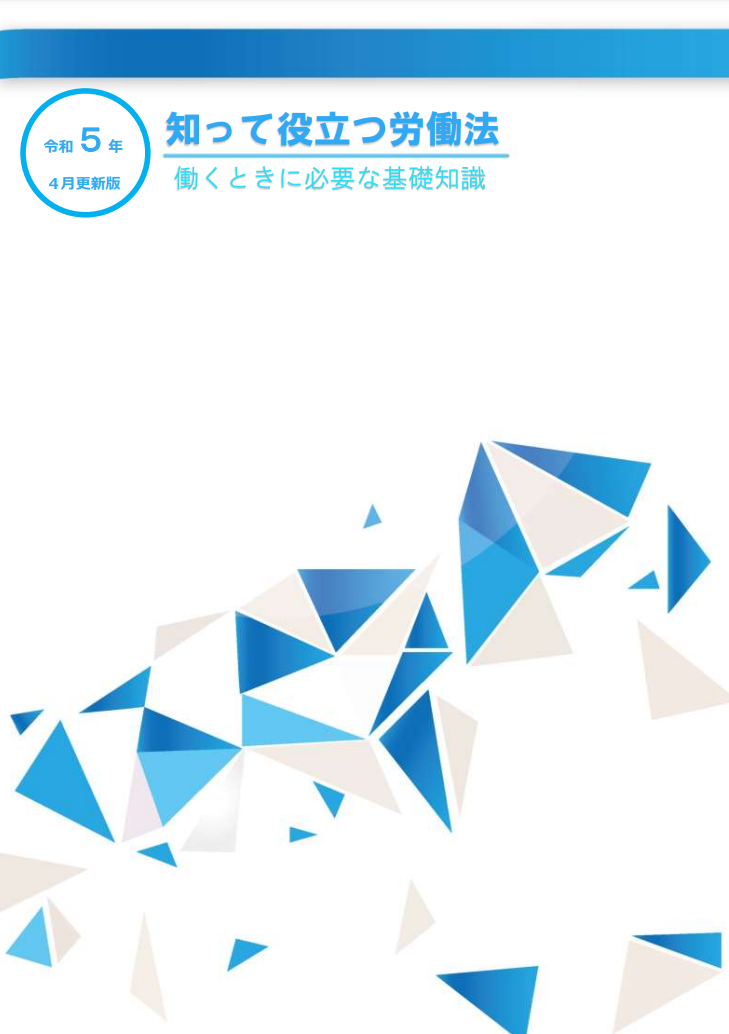 試験対策が難しい、労働基準法や労働契約法などの労働関連法規に関する基礎知識について、わかりやすくまとめている資料です。厚生労働省が制作をしており、PDFファイルを無料でダウンロードできる点が◎です。受験にあたって、一読をおすすめします。
試験対策が難しい、労働基準法や労働契約法などの労働関連法規に関する基礎知識について、わかりやすくまとめている資料です。厚生労働省が制作をしており、PDFファイルを無料でダウンロードできる点が◎です。受験にあたって、一読をおすすめします。
令和5年に改訂版が出ました。版権フリーで、英語版、中国語版、ベトナム語版もあります。
おすすめ指数は、![]()
労働法[第4版]
労働関連法規に関する入門書。法律関係の書籍の中では比較的読みやすく、労働関係法の全体像や各規定の理解に役立ちます。
職場等で法的な問題が生じる「SCENE」での問題提起や、ハラスメントなどの身近な問題を取り上げた「コラム」など、労働法への興味をひく工夫があります。
おすすめ指数は、![]()
実技(論述・面接)試験対策の参考書編
マイクロカウンセリング技法-事例場面から学ぶ(福原眞知子著)
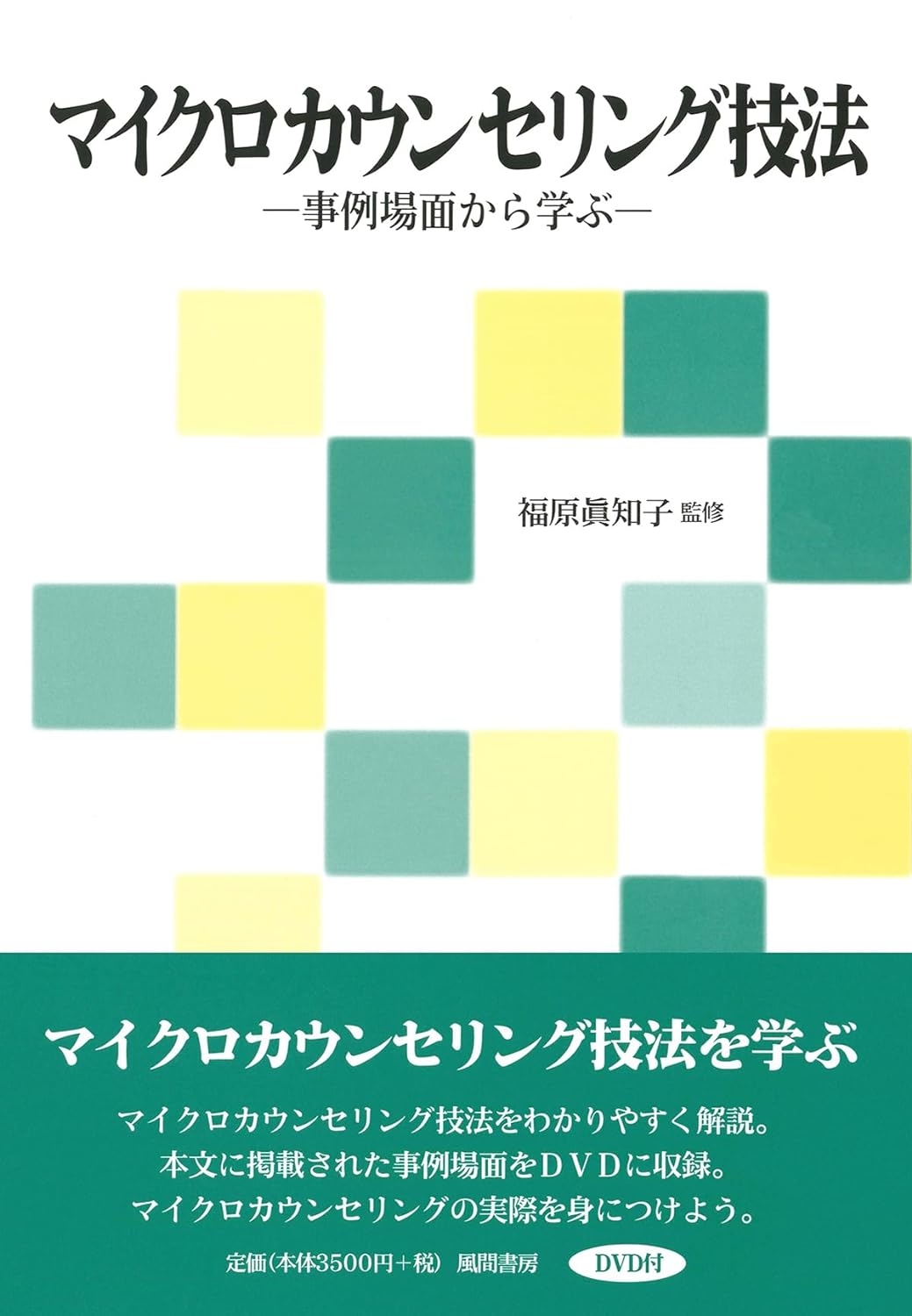 【参考書】技法習得のための知識だけではなく、事例場面の逐語録を用い「良い例」と「悪い例」を確認し、その場面展開に関する解説があるなど、紙の本とは思えない実践的な演習に繋がる良書です。
【参考書】技法習得のための知識だけではなく、事例場面の逐語録を用い「良い例」と「悪い例」を確認し、その場面展開に関する解説があるなど、紙の本とは思えない実践的な演習に繋がる良書です。
おすすめ指数は、![]()
DVDには4つの面接事例が収録されており、逐語録とは違った気づきも得られます。実技試験に向けた自習用教材の決定版と言えるでしょう。
「経験代謝」によるキャリアカウンセリング(立野了嗣著)
【参考書】JCDA創始者の一人であり、前理事長、立野先生の著書。市販書籍で珍しい、経験代謝の解説書であり、ケーススタディも多くJCDA受験者は読んでおきたい一冊です。
おすすめ指数は、![]()
必読とまでは言いませんが、経験代謝の理論の思考訓練ができる良書です。合格後には、協議会受験者にもおすすめです。
手前味噌ですが…。試験対策テキストや問題集のご案内
キャリアコンサルタント学科試験テキスト&問題集(原田政樹著)
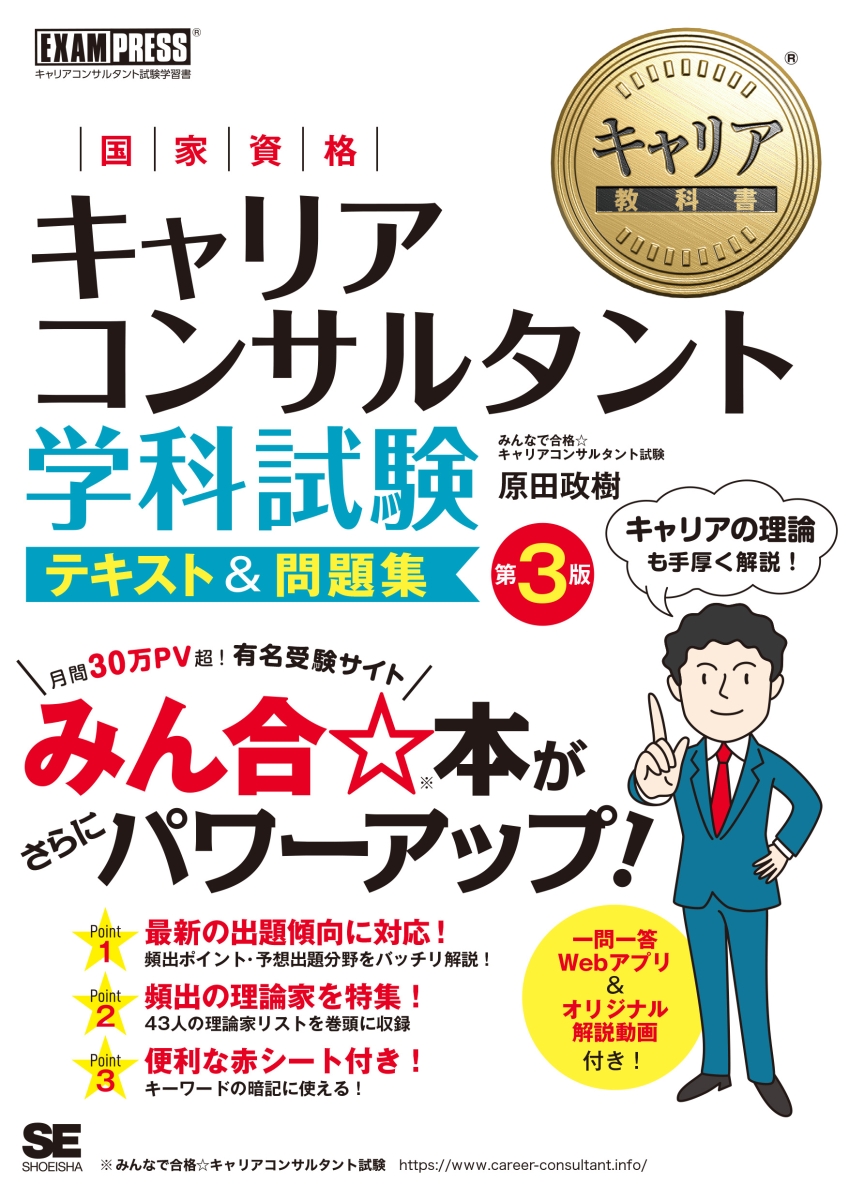 みん合が本になりました!
みん合が本になりました!
これまでの出題項目を中心とした「ポイントまとめ」と、過去問題の改題による「一問一答問題」を掲載し、効率よく知識が身につき、合格力を養成できる一冊です。
赤色チェックシートが付属し、キーワードの暗記や解答確認に役立ちます。みん合の持つ、合格ノウハウをたっぷり詰込みました。
2023年7月に第3版をリリースしました。
購入はこちら【Amazon】
キャリアコンサルタント学科試験「総仕上げ問題集」(原田政樹著)
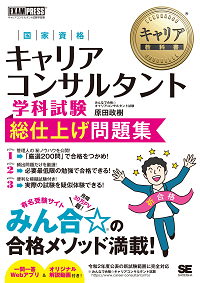 過去問題を研究し尽くして作成した四肢択一式問題150問と本試験を想定した模擬問題50問の合計200問により、試験対策の総仕上げができる一冊です。
過去問題を研究し尽くして作成した四肢択一式問題150問と本試験を想定した模擬問題50問の合計200問により、試験対策の総仕上げができる一冊です。
出題範囲ごとに出題傾向や対策のポイントをまとめたページを一読してから、四肢択一式問題を解くことで、試験対策のポイントや実際の試験での解き方を実感できる、合格対策に必携の一冊に仕上がりました。合格への勘どころを掴み、ラストスパートに役立つ一冊です。初版が最新です。
私ならこう使う!参考書・問題集は厳選して過去問中心の学習を。
教材の好みは、人それぞれですから、上記ガイドやおすすめ指数は、あくまで管理人の個人的な意見として参考にしてください。
ちなみに、私ならば…、という勉強法はこちらです。
①「養成講座テキスト等」の理解が不十分であったとして、まずは「国家試験過去問」をやってみます。
まずは1回分を通しで解いてみましょう。試験の全体像や出題内容のバランス、レベル感を感じるともに、出題範囲表に基づいて、ほぼ一定の割合(問題数)でその内容が出題されていることを体感しましょう。
その際には、当サイトの過去問解説に出典として表示されている、「キャリアコンサルティング理論と実際6訂版」や「新版キャリアの心理学」などを、出題箇所を中心に読み込みます。
書籍のこの2点はマストなのではないかと捉えています。
ただし、これらの参考書をすべてを精読、読破しようとしたら時間がかかりますし、大変です。それは、興味があれば、興味のある箇所を確認する、という姿勢で良いです。
あくまで、出たとこチェックをおすすめしています。
よく出題されている内容などや独特な表現が明らかになってくることでしょう。
また、上記の「ジル資料」と「知って役立つ労働法」はPDF(無料)で入手できますから移動時間やスキマ時間に読むのも良いでしょう。
②出題内容の輪郭が掴めましたら、これまでに実施された「国家試験過去問」について、なるべく多くの回を解いてみることを、おすすめしています。
これまでのアンケートでは、過去問は10回分以上やっている方の合格率が有意に高くなる傾向がありますが、まずは3回分、6回分…と徐々に回数を増やしていくと良いでしょう。
もちろん、得意、不得意が誰しもあるものです。不得意の克服と得意の定着には、過去問を出題範囲ごとに横断的に解く、「ヨコ解き」で効率よく学習しましょう。
過去問の解き方(ヨコ解き)や問題を解くときの注意点などについては「過去問の解き方、私の場合」をご覧ください。
③よく出題されている「各省庁資料」の読み込みや、「国家試験過去問題」の繰り返し、間違えた問題は再度間違えることが無いようによく復習をして総仕上げです。
キャリアコンサルタント試験の受験者は、公私共にご多忙な方が多い印象があります。
移動時間やスキマ時間の有効活用が合格のカギを握ります。
移動時間やスキマ時間には、上記の「テキスト&問題集」や「総仕上げ問題集」や、みん合サイトで知識を確認しましょう。
基礎固めに「テキスト&問題集」、合格力養成に「総仕上げ問題集」の活用がおすすめです。
皆様の時間は有限です。
あれもこれもと中途半端にやるよりも、厳選した素材を徹底的にやりこみ、自分のものにすることが大切です。未消化のものを増やしてはいけません。生きた素材としては、私はやはり「過去問」での知識の確認(インプット)と、繰り返し解くこと(アウトプット)が、最も効果的だと考えています。
昨日までに知らなかったことを、今日、明日に知っていきましょう。
その積み重ねが、合格と自己実現につながると信じて。
応援していますので、共に頑張っていきましょう。
(2024年3月改訂)